【この物語はフィクションです。】
「お腹痛いし……頭も痛い…」
これを聞くのは何度目だろうか、ため息をつきながら階段をおりると、いつも通り学校に休みの電話をする。
お腹が痛いのも頭が痛いのも嘘だというのはわかっていたが、いつも問いただすことはできない。
本当に体調が悪いかもしれないという可能性があるからだ。
でも、病院の診断は異常なし。もう何がなんだかわからない。
学校でいじめられているのだろうか、人間関係がうまくいっていないのだろうか
頭の中は不安でいっぱいだ。
思い返すと息子が学校を休み始めて一週間、仕事や家事に追われて息子のことをしっかり考えていなかったような気がする。
息子を起こしに行き休むことを聞き、学校に電話をする。そしてすぐに家事をこなし、仕事に行く。
夫もあまり息子が学校を休むことには関与しようとしない。家事をするのも、息子の面倒を見るのも全部自分だ。それに加えて仕事もしている。
そんな毎日で息子だけでなく、なんだか自分まで疲れてしまっている。
今日は久しぶりに仕事が休み。息子と話をしようと思ったが、いろいろな不安が頭をよぎり、話をするのはやめておくことにした。
そういえば、息子が生まれてからあまり1人で外出することはなかった。
仕事や家事に追われて、趣味を楽しむことなんてできなかった。
息子が生まれる前はよくカフェで読書をしたものだ。
そんなことを考えていると無性にカフェに行きたくなり、気分を変えるために行きつけだったカフェに行くことにした。
まだあのお店はやっているのだろうか、何年も前のことだから不安である。
不安と期待を胸にカフェがあった場所まで行く。
するとそこにあったのは、商業ビルでカフェはなかった。
ここ数年で都市化したこの町の景色も随分変わった、落ち着いた雰囲気だった町はビルが並ぶオフィス街になってしまったのだ。
なんでこうも悪い事が続くのか、ため息をつきながらとぼとぼ歩き出した。
もう30分は歩いただろうか、ふと頭をあげると暗い路地裏を歩いていた。
まるで自分の暗い気持ちをそのまま表したような路地裏で気味が悪かった。
早く抜け出して大通りにでようと早歩きをしだすと、正面にに古びたお店を見つけた。
看板にはカフェの三文字、古い外観だがなんだか不思議な魅力を感じるお店だった。
その魅力に惹かれたのか気付いたら店のドアを押していた。
「いらっしゃいませ」
50代くらいの店長らしき男性がはにかんでこっちを向いている。
路地裏にあるのに、意外にも店の中は込んでいた。テーブル席は埋まっていたので、仕方なくカウンター席に座る。
「お客さん、何かありましたか?すごく落ち込んでみえますよ」
そういいながら、店長らしき男性はお手拭きと水を出した。
「はあ…そう見えますか…」
「私でよかったら話は聞きますよ。」
「…」
「……実は中学生の息子が一週間前から学校に行かなくなりまして、どうしたらいいのかわからないんです。」
はじめて会った人に悩みを話すなんて自分でも不思議だったが、自然と話していた。
「そうですか、それは大変なことでしょうな。あなたは…」
ジリリリリン
男の声を遮るようにして電話がなる。
電話が終わると、男は困った顔をしてこちらを見る。
「申し訳ないのですが、急用ができまして、話を聞けなくなってしまいました。
あ、そうだ、」
そういうと男性は横を向き、奥のほうに座っている若者に声をかけた。
「松岡君、君大学でカウンセリング習っていたね、僕の変わりにこの方の話聞いてよ」
「はあ、別にいいですけど。
あとカウンセリングも学んでますですけど、それだけじゃないです。大きく言うと心理学を学んでます。」
「店長さん、別にそこまでしなくても大丈夫ですよ!」
その若者に迷惑をかけるからというよりも、相手が大学生だということにあせりと不安を感じた。
「大丈夫ですよ、お客さん。この子凄くいい子ですから」
そういうと男は店の奥に行ってしまった。
大学生は隣の席に座った。
「で、どうしたんです?」
自分は大人なのに大学生は緊張も不安もない表情でこちらを見ている。
容姿は若いのに、なんだか大人の雰囲気を感じる。不思議な感じがする青年だ。
わざわざこっちまで来てくれたことだし、仕方なく悩んでいることを青年に話した。
「で、何が問題なのですか」
「え、ですから今言ったように息子が学校に行かなくなってしまって……」
「息子さんが学校に行かなくなったのもわかりました。原因がわからないのも理解しました。
ですが、その何が問題なのですか?」
「ですから学校に行っていないから行かせないと、、そのためには原因を、、」
「あなた、息子さんの気持ち一度でも考えました?息子さんのことを思っていますか?」
「はい?」
「あなたは息子さんが学校に行かないことを問題としている。そうですね?」
「まあ、そうです。」
「じゃあ、なんで学校に行かせないといけないんですか?」
「…」
「……それは、学校で勉強するのが当たり前だからです。あなただって学校で勉強したでしょ、だから今大学に通えているのでしょう。
今の時代、大学を卒業しなければ、いい会社には就職できないでしょ。
一流大学に入って、一流企業に就職して幸せな将来を過ごして欲しい。全部息子のことを思ってるんですよ!」
大学生が上から言ってくるようで少し腹が立ってきた。
「ほら、やっぱり息子さんの気持ちをわかっていない。」
「なんですか!失礼ですが、あなたよりは息子の気持ちは理解しています!じゃあ、息子に会ったこともないのにあなたは息子の気持ちがわかるんですか?」
「いえ、僕には息子さんの気持ちはわかりません。」
「ほらみなさい、大学で心理学を学んでるようだけど、やっぱりあなた何もわかってないじゃない」
「そうですね、わからない。理解しようとはしますが、わかったつもりにはなりません。」
「……もういいです!この話は終わりにしましょう!ありがとうございました。」
そう言うと、水を飲み干し、帰ろうとした。
「では、お母さんは息子さんが一流大学に行って、一流企業に入りたいと言っているのを聞いたのですか?」
「それは……
でも、そうでしょう!誰でも幸せであったほうがいいにきまってる。」
「では、息子さんにとっての幸せとは一流企業に就職することですか?」
「…」
「一流大学に入って、一流企業に就職する。一般的に言えば、成功かもしれません。
しかし、それは誰の幸せで、誰の願望なのでしょう。」
「なによ!私が自分の願望を子どもに押し付けてるとでもいいたいの?
私の息子を思う気持ちは偽りとでもいいたいの!」
「違います。あなたは息子さんのことを思って幸せになって欲しいと思っている。
それは本当に素晴らしいことです。愛からの思いでしょう。子どもがいない僕にはできません。
でも、ただ少し常識にとらわれてしまってしまって、愛が形を変えてしまっています。
はたして学校に行かなければ、幸せになることはできないのでしょうか。
息子さんが落ち込んで、元気がない今考えるべきなのは学校のことでしょうか。」
「…」
「学校に行くのは大事なことです。でも、今一番大事にすることは何でしょう。
そのとき学校に行かないのは問題でしょうか」
何も言えず、席を立ち上がる。
そのまま何も言わずに、店を出て行く。
大学生はそれをとめることはしなかった。
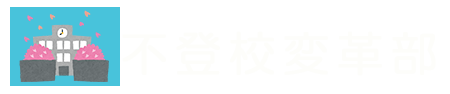













コメントを残す