【この物語はフィクションです。】
「お前気持ち悪いんだよ!」
近くで子どもの声が聞こえた。
カフェで腹がたっていたのもあったのか、イライラが増す。
「こっちは貴重な休みを使って、図書館で不登校について調べてるのに…」
カフェを出てからずっと大学生が言った言葉が頭から離れない。
自分の理想や願望を子どもに押し付けていたのだろうか。
そういえば、息子が将来何をしたいのか、何に興味を持っているのか知らない。
やはり、息子にとって学校が重要なものではなかったら…嫌なものだったら…
いや、違う。私は息子のためを思ってる…そのために学校も行かせなければ…
所詮、心理学をかじっただけのの大学生。専門家でもない。
そんな人の言葉を信じるべきではない。
しかし、なぜか心がもやもやして気持ち悪い。
その気持ち悪さを解消するためだろうか、専門家の本を図書館で読んでいた。
「お前、いつも本読んでて気持ち悪いんだよ!」
見たところ小学生のけんからしい。
「僕が本を読むことと君には何も関係がないじゃですか」
「そのすかした態度が気に食わないんだよ!
いいか、今日はスポーツ大会に向けたクラスサッカーの練習の日だろ」
「自由参加と言っていましたが…」
「スポーツ大会は明後日だぜ、練習は何よりも大切なことだろうが」
「僕も今大切なことをしていました。」
「は?本読んでただけだろ、そんなのいつも読んでるじゃねーか」
「僕にとっては大切なことです。」
「みんな練習来てるだろ!お前だけ来てないじゃないか」
「ですから、今日は自由参加の日でしょう。出るべき練習には出ています。」
「大会は明後日だろ!そのためにみんな来てんだよ!それよりも本を読むのが大事なのかよ」
「はい、大事です。
さっきからみんなみんな言ってますけど、必ずしも多くの人と同じ行動をしなければいけないのでしょうか?」
「そうだろ!みんなと同じことしなけりゃからかわれるし、いじめられるだろ」
「じゃあ、みんなが本を読み出したらあなたも読むんですね。」
「それは……読む!読むに決まってるだろ」
「僕があなただったら読みません。楽しくないから」
「楽しくないとかじゃねーよ!みんなと同じことをすることに意味があるんだよ」
「あなた好きなことないのですか?」
「サッカーだよ、サッカーが大好きだ。」
「サッカーをしてるとき幸せですか?」
「そりゃ、楽しいからなあ」
「じゃあ、好きなサッカーを禁止され、本を読まなくならないといけなくなったら?」
「そんなことあるわけねーだろ、さっきから何言ってんだ!ほら、行くぞ!」
そう言うと本を読んでいた男の子は連れて行かれた。
あの子大人だ。確かに大会が近いからってみんなに合わせる必要はない。
価値観の違いがよくわかってる子だ。それだけに、無理矢理連れてかれてかわいそうだ。
感心しながら本を読むのを再開する。
かなり詳しく書いてある専門書を持ってきてしまったらしい。専門用語ばかりで何が書いてあるかわからない。
そんなとき大学生の言葉が頭の中で流れた。
「一流大学に入って、一流企業に就職する。一般的に言えば、成功かもしれません。
しかし、それは誰の幸せで、誰の願望なのでしょう。」
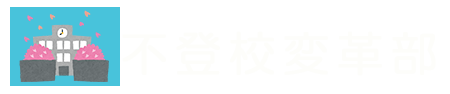













コメントを残す